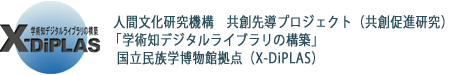採択プロジェクト
2024年度採択プロジェクト
以下、ID番号前のABCは支援カテゴリーを示す。カテゴリーの詳細はこちら
A ID:MDL2024A01
| 申請者 | 松浦直毅(椙山女学園大学・人間関係学部・准教授) |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(A) |
| 課題名 | 学際的統合研究によるアフリカにおける人と動物の相互関係の解明とその実践への応用 |
| 研究期間 | 2021〜2025年度 |
本プロジェクトの支援内容
霊長類学者 西田利貞が1960年代から1970年代にかけてタンザニアやコンゴ民主共和国の大型類人猿生息地で撮影したスライド写真約5000点をデジタル化・データベース化した。研究の進展につれて、研究対象である大型類人猿や現地トレッカーたちとの関係の変化を追うことができ、異文化コミュニケーションおよび異種間コミュニケーションのプロセスをうかがうことができる。地域史のみならず科学史または学術史の観点から興味深い資料である。
A ID:MDL2024A02
| 申請者 | 松田素二(総合地球環境学研究所特任教授、京都大学名誉教授) |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(B) |
| 課題名 | 現代世界の危機に対処する集合的創造性に関する日常人類学的研究 |
| 研究期間 | 2023~2025年度 |
本プロジェクトの支援内容
文化人類学者 米山俊直が1960年代から1990年代にかけて、ザイール、タンザニア、マリ、モロッコ、中国、日本などで撮影したスライド写真約7000点をデジタル化・データベース化した。米山氏の膨大な著作と照合できる資料であり、米山氏の研究の足どりを追うとともに、現代における民間交流の変化や持続を考察することが期待される。
A ID:MDL2024A03
| 申請者 | 澁谷由紀(京都大学・東南アジア地域研究研究所・連携研究員) |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(B) |
| 課題名 | ベトナム紅河デルタ村落における共同体の再編-生計の多様化と生活の安定化 |
| 研究期間 | 2021~2025年度 |
本プロジェクトの支援内容
ベトナム史学者 澁谷由紀が1990年代にベトナム村落部で撮影したスライド写真約6000点をデジタル化・データベース化した。写真からは、ベトナム村落部の景観が近代化していくさまを追うことができる。村落部でカメラを持つ人が少なかった時代の記録であるため、研究者のみならず現地の人たちとも共有することで、地域研究全般の進展が図れると期待できる。
A ID:MDL2024A04
| 申請者 | 佐藤浩司(国立民族学博物館・外来研究員) |
|---|---|
| 研究種目 | |
| 課題名 | 三次元CGを利用した民族建築デジタルアーカイブの構築 |
| 研究期間 | 2008~2018年度 |
本プロジェクトの支援内容
民族建築学者 佐藤浩司が1985年から1987年にかけてインドネシアで撮影したスライド写真約7000点をデジタル化・データベース化した。撮影された建造物の一部は、建築学の観点から実測・作図されたものもあり、撮影当時の東南アジアの性格を多角的に知るてがかりとなる。歴史記録としての価値が高い資料である。
A ID:MDL2024A05
| 申請者 | 池谷和信(国立民族学博物館・名誉教授) |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(B) |
| 課題名 | 装飾文化からみたアフリカ史の再構築に関する研究 |
| 研究期間 | 2020~2022年度 |
本プロジェクトの支援内容
環境人類学者 池谷和信が1980年代から2000年代にかけてアフリカ各地で撮影したスライド写真約4000点をデジタル化・データベース化した。南部アフリカのボツワナで撮影した狩猟活動の写真や、アフリカ地域で撮影した装飾品(とりわけビーズ装飾品)の写真は、各地の地域性とその変遷を追跡するためのまたとない資料である。ボツワナに関してはとくに通時的な世相の比較を、他の地域に関してはとくに共時的な世相の比較を明らかにすると期待できる。
2023年度採択プロジェクト
A ID:MDL2023A01
| 申請者 | 井上卓哉(静岡県富士山世界遺産センター・学芸課・准教授) |
|---|---|
| 研究種目 | 関連研究なし |
本プロジェクトの支援内容
文化人類学者 周達生が1970年代を中心に撮影したスライド写真約6,700点をデジタル化・データベース化した。中国が改革・開放政策を開始する以前の写真も含まれ、近代化が本格化する以前の中国の都市や農村部を捉えている。中国現代史を物語る資料として貴重である。
A ID:MDL2023A02
| 申請者 | 岡田恵美(国立民族学博物館・人類基礎理論研究部・准教授) |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) |
| 課題名 | 南アジアのポリフォニー民謡に関する音楽民族学研究―インド・マニプル州ナガを中心に |
| 研究期間 | 2020~2023年度 |
本プロジェクトの支援内容
写真家 森田勇造が1978年と1979年にインド北東部の山岳地域で撮影したスライド写真約4,000点をデジタル化・データベース化した。この地域は21世紀にいたるまで外国人の旅行がむずかしかった地域であり、写真そのものがめずらしい。歴史的資料として活用しうるほか、日本との交流が始まった同地の研究機関をとおして写真の「現地還元」をおこない、学術分野と民間交流分野におけるいっそうの関係強化が期待できる。
A ID:MDL2023A03
| 申請者 | 竹村嘉晃(平安女学院大学・国際観光学部・准教授) |
|---|---|
| 研究種目 | 国際共同研究加速基金 |
| 課題名 | 移民の身体ポリティクス―インド舞踊のグローバル化とエージェンシー |
| 研究期間 | 2018~2023年度 |
本プロジェクトの支援内容
民族音楽学者 寺田吉孝が1980年代から2000年代にかけてインド各地で撮影したスライド写真約1,600点をデジタル化・データベース化した。写真からは、1990年代以降に著しいグローバル化を経験したインドの都市部や村落部のかつてのようすをうかがい知ることができる。景観変化と並行して芸能のありかたがどのように変化してきたかを分析するうえでも好材料である。
B ID:MDL2023B01
| 申請者 | 末原達郎(京都大学・名誉教授) |
|---|---|
| 研究種目 | 国際学術研究 |
| 課題名 | アフリカにおける食糧生産とその社会経済的背景に関する研究 |
| 研究期間 | 1992~1994年度 |
本プロジェクトの支援内容
熱帯アフリカ農業の研究者 末原達郎が1980年代から1990年代後半にかけてザイール(現 コンゴ民主共和国)やタンザニア、モロッコなどで撮影したスライド写真約5,200点をデジタル化・データベース化した。1990年代のクーデターによって長期滞在調査がむずかしくなる以前の旧ザイールのようすをはじめ、変容の著しいアフリカ各地の農村部のようすが捉えられている。熱帯アフリカの農業について実施された他のプロジェクトもX-DiPLASは支援しており、地域間比較や時間的比較がおこなわれることも期待できる。
C ID:MDL2023C01
| 申請者 | 中村真里絵(愛知淑徳大学・交流文化学部・助教) |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) |
| 課題名 | 世界遺産バンチェン遺跡の遺物の古美術品化とその価値づけをめぐる文化人類学的研究 |
| 研究期間 | 2019~2023年度 |
本プロジェクトの支援内容
横田正臣が愛知県新城市に開設したヨコタ博物館の収蔵資料の写真(支援開始時点でデジタル化済み)約7,000点をデータベース化した。これにより、東南アジア地域(タイなど)の物質文化について研究を進めるうえで貴重な博物館資料を一覧できるようになり、研究資料の共有にもとづいて国境をまたいだ共同研究の道を開くことができた。
2021年度以前に採択されたプロジェクト
X-DiPLASの開始(2022年4月)に先立って、旧DiPLASの枠組みのもとで6年間に75件の支援をおこないました。
詳しくは旧DiPLASサイトの採択プロジェクトのページをご覧ください。