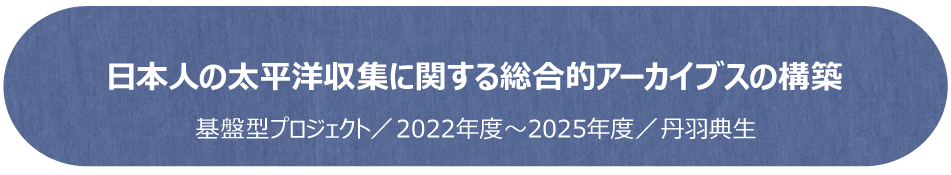プロジェクトの目的
本プロジェクトは、本館所蔵オセアニア関連資料を地理的歴史的に検索するアーカイブスの作成を目的としている。本館オセアニア関連資料の特色は、戦前のアーカイブス資料から戦後の学術調査による標本資料コクレションまで、長い時間幅のもとで、日本人によるオセアニアにおける収集史を反映した世界的な記録の集積という点にある。本プロジェクトでは、本館のオセアニア関連収蔵品のもつ意義を示しながら、歴史的背景を併せて検索可能なアーカイブスを構築することが目的である。
具体的には、日本とオセアニアの関連年表を作成し、そこに個別のコレクション資料等に関連研究資料を付加した上で紐付ける。たとえば、各コレクション等は、通常個人名や探検隊単位でまとめられているため、個別の文脈を超えた国や地域との関連性が希薄となるが、本アーカイブスを通じて、日本とオセアニアの領域的な関係を時代と対象地域の文脈に位置づける。またそれらの核として、朝枝利男コクレションと大島襄二コレクションを取り扱う。前者は国際共同調査研究を通じて調査資料の拡張をはかり、後者は大島の年譜・著作一覧を作成、写真資料と有機的に関連付けたデータベースを構築して、時代に位置づける。以上を通じて、日本におけるオセアニア資料の収集・蓄積の歴史の概観を本館資料から示すと同時に、個別のコレクションに基づく成果を公表することができる。
プロジェクトの内容
本プロジェクトは、本館に所蔵されたオセアニア関連資料の戦前から戦後までの総合的アーカイブス構築を目的としている。核とするのは、朝枝利男コレクション、大島襄二コレクションとして、それ以外の既存の諸資料と連携させた仕様を考えている。プロジェクトの内容としては、2段階で進める。
まず日本とオセアニアの関係を地理的・時代的に位置づける年表を作成する。そしてこの年表の当該箇所に、本館データベース上に個別に置かれている各コレクションへのリンクを張るかたちにする。閲覧者は、年表と各コレクション等の配列から、日本におけるオセアニア資料の収集・蓄積の歴史とそれぞれの時代背景の把握が可能となる。紐付けるコレクション等としては、戦前(杉浦健一、土方久功、朝枝利男)、戦後(泉靖一と京都大学学術調査隊写真コレクションのオセアニア部分)を候補とする。その際、日記やフィールドノートなどを適宜閲覧しながら、可能な範囲で各人の略年譜や業績一覧などの参照資料を作成して付加する。
そうした全体的な枠組の中に位置づけて、朝枝利男コクレションの国際的な共同調査と大島襄二写真コレクションのデータベース作成を行う。前者はすでに構築された朝枝利男データベースを活用して、日米英の博物館と相互に連携して国際的な太平洋資料コレクションの調査を行う。具体的には、カリフォルニア科学アカデミー、ケンブリッジ考古学人類学博物館の国際共同研究員と連携しつつ、在外関連資料の調査を行い、戦前期の太平洋コレクション収集史の中に本館資料を位置づけて研究する。
後者は、地理学者の大島襄二が、1967年から1991年にかけて世界各地で撮影した7889件(内オセアニア関係は、4271件)に及ぶ写真からなり、そのなかには漁労文化や地域研究上の重要な写真が含まれている。オセアニアを幅広く、時代的にも植民地から独立期にかけてという端境期に位置するため、本プロジェクトに適した資料と考える。データベースの作成にあたり、資料の基本情報の精度の向上と拡充及びソースコミュニティからのフィードバックを得るための調査を、関連資料を所蔵するパプアニューギニア国立博物館の国際研究協力者及びトレス海峡資料の総合的な調査プロジェクトを推進しているオーストラリア国立大学の国際共同研究員と連携してすすめる。データベースの使用言語は基本的に日英両言語とし、併せて大島襄二の年譜・著作一覧を作成することで、本館所蔵の写真資料と彼の著作・論考等との有機的な関連付けが可能となる。以上のようにして本館資料を総合することで、それらを研究に供するのみならず、標本資料収集地の人びとや一般社会に対しても、それぞれの文化や歴史への洞察を深める資料群とすることに資する。
期待される成果
期待される成果としては、戦前から戦後に至る本館所蔵オセアニア関連資料の窓口となるアーカイブスの作成を行うことがあげられる。現在の民博におけるコレクションとアーカイブスは、相互に関連性が希薄で別個に独立して存在している。本プロジェクトで構築予定のアーカイブスは、それらを日本とオセアニアの関係史という視点から包括して、標本資料・映像音響・学術論文等の諸資料の横断的かつ有機的な利用を促進することが可能となる。学術論文等は、進行中の共同研究(「日本人による太平洋の民族誌的コレクション形成と活用に関する研究」)と連動しながら、朝枝利男コクレションの資料精査を行う、英語による論集の刊行を計画している。それ以外にも本プロジェクトの活動と連携した論考の寄稿を検討している。国際シンポジウム等は、現地人の研究者であるパプアニューギニア博物館のスタッフやオーストラリア国立大学の国際共同研究員と連携しつつ、行うことを計画している。
2024年度成果
データベースに搭載する資料の整理と精査をすすめた。残されていた箇所の地域(大島襄二コレクションにおけるオーストラリアのトレス海峡及びノーザンテリトリー、京都大学学術調査隊のフィジーなど)の写真と付加情報の整理は概ね完成した。
朝枝利男コレクションとの関係では、アメリカ合衆国ユタ州のトパーズ収容所の跡地及びトパーズ博物館にて資料の調査と関係者からの聞き取りを行った。朝枝の収容所時代の水彩画の作画地点の概略を把握し、収容所において朝枝と面会していたデルタ界隈の名望家の情報を確定できた。後者の博物館については研究者ネットワークの構築も行った。またこれまでのフォーラム型での調査結果を反映させた単行著(『ガラパゴスを歩いた男――朝枝利男の太平洋探検記』教育評論社)を刊行し、関連する英文での編著の編集にも着手した。
大島襄二コレクションに関しては、国際共同研究員や現地協力者と連携のうえ、2025年度開催予定のシンポジウムの準備を進め、テーマの設定、開催日・登壇者等の調整を行った。また本館の大島襄二コレクションを活用した2025年にオーストラリアで開催予定の展示の準備とそれを一部巡回させる形で2026年度に国立民族学博物館にて開催予定とする展示案の素案を作り、文化資源プロジェクトにて申請を行った。また資料整理を進めるなかで、大島襄二のご遺族から寄贈を受けた本館未収蔵の写真資料の追加分について整理を進め、来年度以降に開催予定としている国際シンポジウムや展示での活用できるよう整備した。なおシンポジウムと展示をスムーズに進めるために、本館の外国人研究員のもと国際共同研究員のうち1名を2025年度に招聘することが決まっている。
2023年度成果
データベースの入り口となる年表の日本語の箇所は概ね作成した。朝枝利男コレクションの柱としてある朝枝利男の伝記の執筆を進め、国際共同研究員との連携を通じて海外博物館の収蔵資料も活用した草稿を完成させた。またニューヨークのアメリカ自然史博物館、ニューヨーク動物協会にて朝枝利男関連の収蔵資料の調査を行い、これまで未確定であった収蔵品や伝記的情報の確定を行った。データベース関係では、各種水彩画資料の掲載に向けた整理を完了させ、掲載に向けて進めた。あわせて未搭載地域であった写真資料を整理したうえ、データベースに追加した。
大島襄二コレクションに関しては、国際共同研究員は現地協力者と連携のうえ、本館写真資料を使用したオンラインのプロジェクトの紹介ページの作成、日本文化人類学会第57回研究大会における分科会開催、『月刊みんぱく』2023年12月号での特集号の掲載を行った。パプアニューギニア関係の写真資料については、昨年度に続き国立博物館・美術館と情報の交換を図ったほか、ラバウルの博物館と資料の共有しながら研究ネットワークの構築を行った。また資料整理を進めるなかで、大島襄二のご遺族から本館未収蔵の写真資料の寄贈を受け、それらの情報を反映させたデータベースに掲載する年譜・業績一覧を完成させた。
それ以外には、本プロジェクトの成果としての日本人の太平洋収拾についてのデータベースに搭載すべく、ポリネシア地域については、京都大学学術調査隊写真コレクションの日英両言語化と被写体事項の確認作業を行った。ミクロネシア地域については、杉浦健一マーシャル関係資料の精査と、杉浦健一に関する年譜・著作一覧を完成させた。メラネシア地域については、泉靖一のパプアニューギニア滞在記の読解のほか、戦間期の本館所蔵コレクションを中心に収蔵の背景の精査、他館収蔵資料や個人蔵資料との調査を通じて比較分析をすすめ、データベースに反映させるための整理を進めた。
2022年度成果
今年度は、日本とオセアニアの関係史に関する本館の総合的アーカイブスについての枠組の検討を進めた。暫定的ではあるが、窓口としてデジタルアーカイブスの表紙に掲載する年表の暫定版を作成した。また国立民族学博物館共同研究「日本人による太平洋の民族誌的コレクション形成と活用に関する研究――国立民族学博物館所蔵朝枝利男コレクションを中心に」(みんぱく共同研究会と略記)のもとで、関連する発表が1回行われた。
朝枝利男コクレションについては、水彩画の分析を進め、査読付論文を一本掲載した。カリフォルニア科学アカデミーに収蔵されている朝枝利男の水彩画は鋭意デジタル化を国際共同研究員がすすめており、オンライン上での公開を計画している。またみんぱく共同研究会のもとで、関連する発表が6回行われた。
大島襄二コレクションと京都大学学術調査隊のコレクションに関しては、外部の専門家の助力を請いながら、被写体の確定と写真資料の日英両言語化をすすめた。大島コレクションに関しては、著作・論考の悉皆調査を行い、年譜と業績一覧を作成している。特に、同コレクションのトレス海峡部分については、国際共同研究員により写真資料の精査が済み、現地コミュニティでの情報収集も進めている。現在、それらの成果を反映させた展示とシンポジウムの立案を計画している。大島及び京都大学学術調査隊の両コレクションのパプアニューギニア関連資料については、共同研究員とともに現地調査を行い、パプアニューギニア大学やパプアニューギニア国立博物館と連携しつつ、コレクションの注釈などについて資料の充実化を図ることための意見交換を行った。非常に好意的な反応を頂いたので、協定の締結を視野に入れつつ次年度以降適宜進めていきたい。また関連するエッセイが1本掲載された。
本館所蔵のメラネシア関連資料については、共同研究員が本巻収蔵資料の調査を行った。関連するエッセイが二本掲載された。マーシャル諸島関係資料については、新型コロナ感染症の感染拡大状況のため現地調査は難しいと判断し、ハワイ大学に滞在して関連史資料の収集・調査をすすめた。
今年度のプロジェクトをすすめるなかで、日本とオセアニアの関係を考えるとき、太平洋戦争の影響を抜きに考えるのは難しいと痛感した。パプアニューギニア諸機関と連携しつつ調査を進め、総合的アーカイブスのなかにも何らかの形で反映させて行きたいと考えている。関連する本館の資料として泉靖一のパプアニューギニア滞在時のレポートと日記があげられる。今年度は当該箇所の日記を閲覧して、必要箇所のデジタル化を行った。