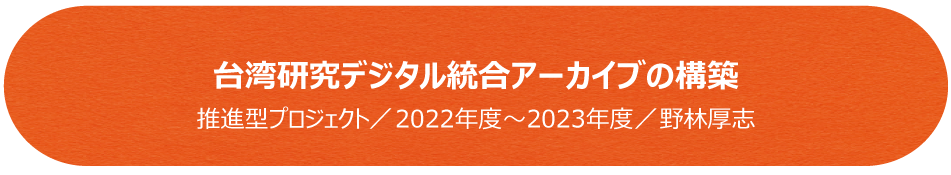プロジェクトの目的
本プロジェクトの目的は、本館に収蔵されている台湾関係資料のデジタル化を促進し、これらをデータベースによって統合し、属性の異なる資料を時間軸と空間軸でつなぐことを可能とするデジタルアーカイブを構築し、それをオンラインで公開することにより、研究者コミュニティにとっての学術資源の共同利用、ソースコミュニティも含めた一般社会と文化資源を共有することである。そのうえで、特に本館の所蔵資料が中心となっている日本統治時代(1895~1945年)における台湾社会を、1)物質文化の変化、2)景観の変化、3)社会生活の変化、という側面から探究することを研究上の目的とする。
従前にあげた変化は、これまでの研究では主として歴史学の分野で進められてきた。とりわけ、申請者の専門領域である先住民研究では、理蕃政策(先住民族の統治政策)、法整備の状況、経済指標といった観点で研究が進められてきた。一方で、こうした制度の変更や統計的に把握できる経済指標からわかる変更と、実際の社会生活の間にはずれが生じることは少なくない。また、社会生活の変化が制度変更や経済指標に影響を与えていたことも十分考えられる。
本研究では従来の歴史研究の蓄積をふまえたうえで、本館が収蔵する標本資料、画像資料、文献資料から得られる台湾社会の情報を連結させ、より粒度の大きな台湾社会の歴史像を描くものである。
プロジェクトの内容
本プロジェクトは、以下の計画を段階的に実施し、本館における台湾研究、植民地研究の強化をはかるとともに、本館収蔵の学術資料の大学共同利用と一般社会との共有を促進する。
(1)台湾研究デジタル統合アーカイブの構築
(2)デジタルアーカイブを活用した国際共同研究の展開
(3)オンライン企画展の企画立案
(1)台湾研究デジタル統合アーカイブの構築
本館に収蔵されている台湾関連資料のデジタルデータ化を促進し、第3期のフォーラム型情報ミュージアムプロジェクトで構築したデータベースプラットフォームを活用したデジタル統合アーカイブを構築する。申請者はすでに本館所蔵の標本資料については、第3期のフォーラム型情報ミュージアムプロジェクトにより、「台湾および周辺島嶼の物質文化」データベースを構築し、日中英でのオンライン一般公開を行い、国内外の研究者、ソースコミュニティ、一般利用者との文化資源の共有をはたしてきた。これらは、主として物質文化という側面から台湾社会や特に先住民族である台湾原住民族の社会や歴史に関する理解を促すための研究に資するものである。
本研究では、これに加えて、社会の様子を具体的に可視化させる画像、詳細な情報を与える民族誌や新聞、機関紙の情報をデータベースに組み込み、1)物質文化の変化、2)景観の変化、3)社会生活の変化、を相互参照できるデジタル統合アーカイブを構築する。
1)については、すでにデータベースの構築は完了しているが、一部の資料画像は旧世代の自動撮影装置で撮影した解像度の低いものであることから、より良質なアーカイブとするために画像の状態を確認し、本館全体の資料画像の撮影計画に合わせながら画像の更新を実施する。
2)については、本館に収蔵されている内田勣アーカイブ、小林保祥アーカイブ、馬淵東一アーカイブの画像資料についてデータベース化し、「台湾および周辺島嶼の物質文化」データベースとの連結を進める。特に内田勣アーカイブについては、本館と学術交流協定を締結している台湾の国立台湾歴史博物館と連携してデータベース化を進める。
3)については、本館に収蔵されている日本統治時代の報告書類(『蕃族慣習調査報告』、『理蕃志稿』、『理蕃の友』『台湾旧慣 冠婚葬祭と年中行事』等)で、著作権が消滅しているもののデジタル化、『台湾日日新報』(マイクロフィルム所蔵)等の関連記事の引用テキストをデータベース化し、「台湾および周辺島嶼の物質文化」データベースとの連結を進める。
また、日本には植民地統治時代に現地で生活をしていた人やその子孫が、台湾に関連した資料を所有していることが少なくない。本研究プロジェクトでは、「台湾研究デジタル統合アーカイブ」のWebサイト、SNSをたちあげ、広く一般からの研究資料の寄贈を受け付け、デジタル資料の蓄積をはかる。
(2)デジタルアーカイブを活用した国際共同研究の展開
(1)と並行しながら、デジタルアーカイブを活用した国際共同研究を、同様な台湾関連のデジタルアーカイブを構築、一般公開している国内外の研究機関と連携し、台湾のミクロストリアについての国際共同研究を展開する。具体的な研究機関として想定しているのは、米国・ラファイエット大学(ポール・バークレー教授)、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館(長谷川賢二副館長)である。
米国・ラファイエット大学は、日本統治時代を中心とした台湾の絵葉書に関するデジタルアーカイブを構築、オンライン公開しており、植民地における景観と表象の研究を進めてきた。徳島県立鳥居龍蔵記念博物館は、本館が収蔵する鳥居龍蔵収集資料のバックデータとなるフィールドノートのデジタルアーカイブを構築、オンライン公開しており、19世紀から20世紀前半の日本の人類学研究の検証を進めてきた。
これらの研究機関に加えて、台湾の国立台湾史前文化博物館、学術協定を締結している国立台湾歴史博物館、神奈川大学常民文化研究所に関係している研究者を中心にした研究チームを組織し、植民地台湾における社会変化を探究するとともに、デジタルアーカイブスにもとづく歴史研究の方法論を検討する。
また、本研究で明らかにしようとする植民地期台湾の変化は、現代の台湾社会の移行期正義の課題とも深く関わるものである。現在、台湾では主として中華民国施政下における政治的抑圧状況に関する移行期正義が問われている。一方で、これらの課題は実体験の世代が減少している日本統治時代にもその背景を求める動きが今後増大することは十分予想される。言説から形成される集団的記憶とは異なる角度からの歴史記憶に資するアーカイブスの形成の国際共同研究を進める。
(3)オンライン企画展の企画立案
共同研究者の数名は博物館に所属することから、デジタルアーカイブを活用したオンライン企画展の企画立案を行う。実際の実施については、企画立案の作業段階での実現性、予算措置等の状況に応じて検討していく。
期待される成果
構築を目指す台湾研究デジタル統合アーカイブは、
1)オンラインによる一般公開
2)民博収蔵の台湾関連の各種資料のデジタル資源化
3)第3期のフォーラム型情報ミュージアムで構築したデータベースを発展させた多言語(日中英)環境とコメント機能を有する双方向型
の特徴をもち、学術コミュニティ、大学共同利用、ソースコミュニティを含めた一般社会と本館の学術資料、文化資源を共有する強力なツールになることが期待される。
また国際共同研究の成果としては、1)物質文化の変化、2)景観の変化、3)社会生活の変化、という3つの観点で台湾のミクロヒストリアを考察する論文集もしくは、学会誌等への特集の刊行を行う。
2023年度成果
1)台湾研究デジタル統合アーカイブの構築とオンライン公開
昨年度に構築した日本語の統合アーカイブの英語版と中国版の基本設計を構築した。統合アーカイブの内容には、(1)本館で進めている研究計画プロジェクト(フォーラム型人類文化アーカイブ、科研費)、(2)フォーラム型人類文化アーカイブ構築のデータベース(「台湾および周辺島嶼の物質文化」データベース、「内田勣アーカイブ」データベース、「小林保祥アーカイブ」データベース)、(3)研究ライブラリ(台湾研究の内外のデータベース、民博開催の展示会アーカイブ、台湾資料所蔵の国内外研究機関・博物館の参照リンク)を含み、台湾に関する人文学研究を推進するうえで有用な統合アーカイブとなっている。
オンライン公開については、資料の肖像権、著作権の確認作業が完了しておらず、次年度に持ち越しとした。
2)対面・オンライン併用による国際共同研究会の準備会合と開催
(1)国際ワークショップ ‘Thinking Hunter-gardeners: Anthropological and Archaeological Approaches.’ の開催
2023年4月24日に、台湾における生態環境の適応を探究する国際ワークショップ ‘Thinking Hunter-gardeners: Anthropological and Archaeological Approaches.’ を対面、オンライン併用で実施し、台湾の主要な生業複合である狩猟農耕の相対化を試みた。外国人特別研究員のYu, Peilin(Boise State University)氏と研究代表者である野林が企画立案し、6人の発表者(共同発表を含む)と22名の参加者による議論を行った。
(2)台湾原住民族、台湾の研究者による資料熟覧と共同調査の実施
2023年6月21日から27日に、タイヤル族および国立台湾芸術大学、国立政治大学の研究者による資料熟覧の共同調査を実施した。調査においては、精査および構築中の「台湾および周辺島嶼の物質文化」データベース、「小林保祥アーカイブ」データベースを試験的に活用し、資料の実見とアーカイブの活用の方法を検証した。また、2023年6月24日(土)には、本研究の代表者が研究代表者である科研費基盤研究A「民族誌アーカイブズとフィールド調査の接合による植民地初期台湾の先住民族社会の探究」(22H00040)との合同の研究会を実施し、現在の台湾における先住民工芸の継承の課題についての議論を行った。
(3)国立台湾歴史博物館とのアーカイブ構築にむけた共同準備
国際学術協定にしたがい、アーカイブ中の「内田勣アーカイブ」データベースの中国語翻訳を共同で進めた。また、2024年3月に野林、寺村、奈良の3名が同博物館を訪問し、アーカイブ進捗の状況の報告、民博の資料を活用した国際連携展示(2024年8月開幕予定)の準備会合を実施した。
3)オンライン企画展の企画立案
本館で実施した企画展「伝統と再生」(1994年3~5月開催)の図録や関連した刊行物、当時の記録のコンテンツ化を進め、Web上での再生展示の設計を行った。テキストの内容については執筆者等の許諾を得ており、次年度以降にオンライン公開を可能とする環境を整備した。
4)論文集(特集)の執筆・編集
国際ワークショップ ‘Thinking Hunter-gardeners: Anthropological and Archaeological Approaches.’の編集を進めた。2024年度に本館『研究報告』に特集として申請する予定である。
2022年度成果
本年度は当初計画をにらみながら、ポータルサイトの利用や運用を検討するなかで、掲載するコンテンツの内容によって、データ化の対象とする研究資料の洗い直しをすすめた。
1)「台湾および周辺島嶼の物質文化」データベースのデータ確認。システムの移行の検討。
著作権、カルチャル・センシティビティの判定をフォーラム型委員会から提供されたアプリを利用して進めた。今年度末(少なくとも来年度当初)までには判定は終了する予定である。データの内容の確認については、共同研究員との協働で進めたところ、表示されているデータにずれがあることが判明している。異なるデータセットの表示方法にシステム上の課題があることから、標本資料を対象とするシステムについては移行を来年度に実施したいと考えている。
2)内田勣アーカイブ、小林保祥アーカイブ、馬淵東一アーカイブの画像資料の公開手続き。
内田アーカイブについては、データと画像番号のふりなおしを完了させるとともに、学術協定の締結機関である国立台湾歴史博物館で中国語への翻訳を開始した。小林アーカイブは共同研究員が中心となりデータを精査し、コンテンツの日本語版が完成している。内容の点から馬淵アーカイブの掲載については対象からはずすことにした。
3)文献資料のデジタル化作業。データ化。
本館収蔵のデータとして、過去の展示会のデータアーカイブの重要性が指摘されたこともあり、1994年に開催された企画展「伝統と再生」、2009年に開催された「百年来的凝視」を対象としたデジタル化を進めることとし、「伝統と再生」のテキストのデジタル化を進めた。
4)オンラインによる国際共同研究会の実施。
COVID-19による感染症の状況が改善されたことから、対面を中心とした研究会を実施した。いずれも共同研究員である長谷川、陳俊男が所属する徳島県立鳥居龍蔵記念館、国立台湾史前文化博物館と協働して開催した。
2023年2月12日 国立台湾史前文化博物館
2023年3月12日 国際シンポジウム「鳥居龍蔵と台湾 ―資料の可能性を探る―」徳島県立鳥居龍蔵記念館
5)「台湾研究デジタル統合アーカイブ」のWebサイトのたちあげ。
「研究プロジェクト」、「ライブラリ」を主要コンテンツとするWebサイトのデザイン制作を完了させた。